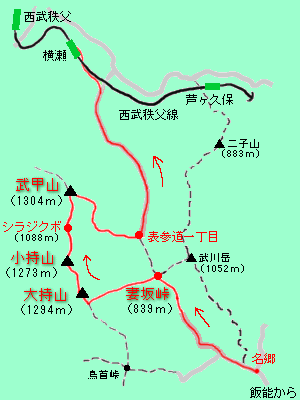| 11:20 |
歩きにくい登り坂
(このあとしばらくは名栗村&横瀬町) |
9349歩 |
妻坂峠を出発すると、いきなり急な登り坂になります。しかも、溝の底に詰まれた土嚢の上を歩く、非常に歩きにくい道です。どうやら、崩れた山道を簡易的に補修したもののようです。 |
| 11:45 |
------- |
10557歩 |
ここで、別の登山者がタバコを吸って休憩しているを見かけました。また、後ろからは、妻坂峠で見かけた人が2人歩いてきていました。追いつかれないように先を急ぎました。(別に追いつかれたところでどうなるわけでもないけど・・・) |
| 12:00 |
------- |
11516歩 |
時刻は正午。右のほうに武甲山(?)が見えます。
道は、急な登り坂になったり平坦になったりの繰り返しです。 |
| 12:20 |
大持山分岐(名栗村・横瀬町&秩父市)
おおもちやまぶんき
 |
12224歩 |
ここで、鳥首峠方面からの道と合わさります。名栗村・横瀬町・秩父市の「市町村」にまたがる場所でもあります。
ここからの景色はかなり素晴らしいです。写真は、ここから南東(名郷方面)を撮ったものです・・・たぶん。どこで写真を撮ろうか考えている間に、後ろから来ていた2人に追い抜かれました。
遠くのほうから、武甲山での石灰岩採掘のための発破(採掘については武甲山の山頂の項目で書きます)の警告放送が聞こえてきました。ここまで来れば、大持山山頂はすぐ近くのはずです。 |
12:34
から
12:37 |
大持山(横瀬町&秩父市)
おおもちやま 標高1294.1m
 |
12642歩 |
関東百名山の一つ・大持山の山頂です。先ほどの大持山分岐ほどの景色ではありませんが、西側の山は綺麗に見えます。(左の写真をクリック)
ここまでは、名郷から3時間20分ほどの、ほぼ標準的なペースで来られました。あくまでも「ここまで」は・・・・・・
先ほど私を追い抜いた2人は食事中のようなので、追い抜き返して、先へ進みました。案内板によると、小持山まで40分、武甲山まで1時間50分とのことです。 |
| 12:53 |
邪魔な岩
(このあとしばらくは横瀬町&秩父市) |
13206歩 |
大持山を出発したらしばらくは下り坂でした。(山頂から歩き始めたのだから当然だけど・・・)
ここには、大きな岩2つが、道をふさぐように並んでありました。その2つの岩の間を通るわけですが、間にも小さな岩があり、かなり邪魔でした。また、左右は急斜面になっているため、この場所自体を避けて通ることも無理でした。 |
| 13:04 |
岩の登り坂 |
13461歩 |
岩がむき出しの登り坂があり、なかなか登るのは大変でした。でも登り終わったと思ったらすぐに下りになってしまいました。よく見たら、横にもう一本細い道があり、そちらを使えばまったく昇り降りをする必要はありませんでした。 |
| 13:10 |
小持山? |
13512歩 |
またも登るのが大変な坂がありました。それを登りきったとき、山頂らしき場所に出ました。大持山を出発してから33分なので、時間からすると、ここが小持山だと思われました。ただし、案内板などは何もありませんでした。とにかく、ここが小持山だと判断して、次のシラジクボを目指しました。
ちなみに、先ほどから何度か話題に出している2人の登山者に、この場所で追い抜かれました。 |
| 13:?? |
急な下り坂 |
?歩 |
山頂らしき場所を出発すると、突然、急な下り坂になり、滑らないように降りるにかなりてこずりました。そんなことで時間をかけてしまったためか、これ以降「2人の登山者」の姿を見ることはもうありませんでした。 |
| 13:33 |
またも岩の登り坂 |
?歩 |
ここにも岩がむき出しの登り坂があり、なかなか登るのは大変そうでした。でも今度は、先ほどの教訓から、わき道を探し出して昇り降りを回避することができました。 |
| 13:45 |
道が不明瞭な場所 |
14345歩 |
道がやや不明瞭になり、本当にここが道なのか不安なまま進み続けました。しばらくしたとき、正面から別の人が歩いてきたので安心しました。 |
13:55
から
14:00 |
小持山(横瀬町&秩父市)
こもちやま 標高1269m
 |
14602歩 |
突然、案内板がある場所に出ました。「まさかここがシラジクボか?」と思い、字を読むと、なんと「小持山」と書いてありました。普通なら40分で歩けるところに、80分近くかけてしまったようです。
ちなみにここは、山頂といってもあまり特徴のある場所ではありませんでした。 |